言論NPOは3月21日、曽我部真裕氏(京都大学大学院法学研究科教授)、成原慧氏(九州大学大学院法学研究院准教授)、若江雅子氏(読売新聞編集委員)の三氏をゲストにお迎えし、言論フォーラム「インターネットの情報規制をどう考えるか」を開催しました。司会は、東京大学大学院総合文化研究科教授で、言論NPOの「日本に強い民主主義をつくる戦略チーム」共同代表を務める内山融氏が務めました。
フォーラムでは、インターネット空間とそれに対する規制の現状、4月施行の情報流通プラットフォーム対処法の評価、若年層のSNS規制といったテーマについて議論が展開されました。
日本の規制は新法が施行されたばかりであり、様子見の段階。しかし、残された課題も多い。トランプ政権下の米国の動向に大きな懸念
言論NPOが昨年実施した民主主義に関する世論調査では、過激な発言や誹謗中傷、様々な偽情報が放任されているX(ツイッター)やユーチューブといったソーシャルメディアについて、65.5%と7割近くの日本国民が何らかの規制が必要だと考えていることが明らかになりましたが、内山氏はこうしたことを踏まえてまず、インターネット空間や規制の現状について各氏の見方を尋ねました。
 これに対し曽我部氏は、インターネット空間の現状については、「不透明」とした上で、「世論の分断が指摘されているが、その度合いを客観的に明らかにできるような指標など、現状分析のツールを開発する必要がある」と課題を提示。ネット上の問題が現実に反映されている例としてしばしば挙げられる兵庫県知事選挙をめぐる混乱や財務省解体デモなどについても「政治への不満の表れかもしれず、インターネット空間特有の問題かどうか、現状では断定できない」と指摘しました。
これに対し曽我部氏は、インターネット空間の現状については、「不透明」とした上で、「世論の分断が指摘されているが、その度合いを客観的に明らかにできるような指標など、現状分析のツールを開発する必要がある」と課題を提示。ネット上の問題が現実に反映されている例としてしばしば挙げられる兵庫県知事選挙をめぐる混乱や財務省解体デモなどについても「政治への不満の表れかもしれず、インターネット空間特有の問題かどうか、現状では断定できない」と指摘しました。
曽我部氏は規制の現状については、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)が4月に施行されることを受けて、誹謗中傷等の権利侵害への対応としては、新法の効果を様子見する段階であると解説。一方、偽情報対応に関しては、「総務省で議論されていたが、止まっている」と説明。今夏には参院選も控えていることもあり、こちらも不透明としつつ、消費者保護、青少年保護の規制立法についても、諸外国と比べると議論が停滞しているとの見方を示しました。
その外国の動向については、トランプ政権発足の前後で様相が異なっていると指摘。米欧間では「温度差こそあるものの、SNSあるいはネット空間の問題について対応が必要という点ではベクトルが合っていた」としつつ、「トランプ政権になってから、欧州は変わらないが、米国はそうではなくなっている」と分析。こうした状況下では、欧州連合(EU)の規制がEU域外の国々や企業に影響を与え、自主的に遵守するようになる現象である「ブリュッセル効果」もどこまで発揮できるか不透明であると語りました。
 成原氏は、何らかの規制自体は必要としつつ、現状でも刑法の名誉棄損罪、侮辱罪、民法の不法行為法、公職選挙法の虚偽事実の公表罪などが既にあることを指摘。新たな規制を考えていくにあたっては「それだけでは不十分なのか、それとも過剰なところがあるのか。こういったことを精査していく必要がある」との見方を示しました。
成原氏は、何らかの規制自体は必要としつつ、現状でも刑法の名誉棄損罪、侮辱罪、民法の不法行為法、公職選挙法の虚偽事実の公表罪などが既にあることを指摘。新たな規制を考えていくにあたっては「それだけでは不十分なのか、それとも過剰なところがあるのか。こういったことを精査していく必要がある」との見方を示しました。
また同時に、「法的な規制はあっても、その執行が上手くいっているかどうかは別問題だ」とも指摘。「公選法で実際に検挙されるかは警察など捜査機関の判断次第なところがあるし、プラットフォーム上の誹謗中傷も削除は事業者の判断に委ねられている」として、この点でも曽我部氏が指摘するような「不透明」な問題があるとの認識を示しつつ、情プラ法下では対応への迅速化とともに、透明化がどのように図られるかを注視する必要があると語りました。
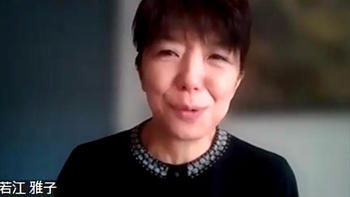 若江氏は、ネット空間の現状についての懸念点としてまず、の追求によってコンテンツが過激化していっていることを挙げ、兵庫県知事選をめぐる騒動もその一例であると解説。「膨大なデータを保有し、それをプロファイリングしてできるだけユーザーを滞在させて広告収入を稼ぐことを目指している。そのためには対象に『刺さる』データコンテンツを出していく必要があるわけだが、それにエコーチェンバー、フィルターバブル効果も相まってユーザーを過激にしていく」としつつ、そもそもプラットフォーム自体がアテンション・エコノミーを追求する性質を内在しているとも語りました。
若江氏は、ネット空間の現状についての懸念点としてまず、の追求によってコンテンツが過激化していっていることを挙げ、兵庫県知事選をめぐる騒動もその一例であると解説。「膨大なデータを保有し、それをプロファイリングしてできるだけユーザーを滞在させて広告収入を稼ぐことを目指している。そのためには対象に『刺さる』データコンテンツを出していく必要があるわけだが、それにエコーチェンバー、フィルターバブル効果も相まってユーザーを過激にしていく」としつつ、そもそもプラットフォーム自体がアテンション・エコノミーを追求する性質を内在しているとも語りました。
若江氏は、日本の規制の現状については、プロファイリングやデータ収集に関する規制の遅れを指摘。「個人情報保護法ではいまだにプロファイリングの定義すらない」と語りました。
海外とりわけ米国については、トランプ政権発足以降の流れを懸念しつつ、特に「国家とプラットフォームが結びついているという、最悪のパターンに陥っている」としました。
情プラ法の実効性には期待できるが、限界もある
 続いて内山氏が情プラ法について、「権利侵害への対応としてこれで十分なのか」などと評価を求めると、若江氏は「期限を区切って迅速な対応が可能になったという点では評価できる」と回答。また、運用状況の透明化を高めさせようとするアプローチについても妥当と評価しましたが、第28条(措置の実施状況等の公表)に関しては、「削除すべきものを削除しなかったり、削除すべきでなかったものを削除するなどのコンテンツモデレーションのエラー率も指標として入れると、きちんと対応しているかどうか判断しやすくなるのではないか」と注文を付けました。また、サンクション(制裁)が不十分であることや、政治家が「本人以外の第三者による削除申請」を行う場合、それが「恣意的なものにならないようにする運用は必要になってくる」とも指摘しました。
続いて内山氏が情プラ法について、「権利侵害への対応としてこれで十分なのか」などと評価を求めると、若江氏は「期限を区切って迅速な対応が可能になったという点では評価できる」と回答。また、運用状況の透明化を高めさせようとするアプローチについても妥当と評価しましたが、第28条(措置の実施状況等の公表)に関しては、「削除すべきものを削除しなかったり、削除すべきでなかったものを削除するなどのコンテンツモデレーションのエラー率も指標として入れると、きちんと対応しているかどうか判断しやすくなるのではないか」と注文を付けました。また、サンクション(制裁)が不十分であることや、政治家が「本人以外の第三者による削除申請」を行う場合、それが「恣意的なものにならないようにする運用は必要になってくる」とも指摘しました。
成原氏も「削除対応の迅速化と運用状況の透明化の二本柱で誹謗中傷対策を進めるとともに、コンテンツモデレーションの透明化を図ろうとする方向性は基本的に妥当」と評価。
同時に課題として、「誹謗中傷対策をして個人の名誉や人格権、プライバシーを守ることは重要であるものの、それは表現の自由との間に緊張関係がある。両者のバランスをいかに取っていくかは常に難しい問題だ」と指摘。正当な批判と誹謗中傷の線引きや、名誉棄損には至らないが個人を傷つけるような新しい類型の言動への対処は、これまで裁判所の判断の積み重ねに拠るところが大きかったものの、これからはプラットフォーム事業者も「そうした難しい判断を迫られることになる」と語りました。コンテンツモデレーションについても、むしろ真面目に取り組めば取り組むほど難しい線引きの問題に直面するとも指摘し、「事業者だけに任せるのではなく、私たちも妥当なバランスを考え、チェックしていく必要はある」と語りました。
曽我部氏は、情プラ法は旧法である「プロバイダ責任制限法から発想、立て付けを大きく変えるものだ」と指摘。プロバイダ責任制限法は「損害賠償責任を一定の場合には免責するということを通じて削除へのインセンティブをつくり出す。同法は民法の特別法だが、これはまさしく民事法的な発想に基づくルールだった」のに対して、情プラ法の場合は、「利用規約に基づく削除に関して一定の義務付けを行う。つまり、透明性、迅速性ということを義務付けるということであり、民事法ではなくて公法的な規律だ」とその性質の違いを明らかにしました。
曽我部氏はその上で、情プラ法の実効性については、ある程度期待はできるとする一方で限界もあると語りました。「削除申し出があった場合には迅速に削除せよ、という法律なので、申し出がない場合には情プラ法そのものの規律が及ばないということになる」とした上で、「実際には削除を申し出るということ自体が必ずしも簡単ではない」と指摘。プロレスラーの木村花さんがSNSの中傷を苦に自殺した問題や、兵庫県知事のパワハラ疑惑などを調べる県議会百条委員会の委員を務めた前県議が自殺したとみられる事件を例としながら、「おそらく、これらの方々は削除申し出をできる状況ではなかったはずだ。誹謗中傷が殺到しているような場合、申し出を待ってから迅速に対処するのではなく、非常ブレーキとも言うべき特別なモデレーションが必要になるのではないか」との見方を示しました。
また、利用規約はあくまでも事業者自身がつくるものであって、国としては「違法情報ガイドライン」など利用規約策定にあたっての参考を提示できるに過ぎないことや、削除に関する判断を誤った場合に制裁を課すことが想定されていないことなども限界点としました。
青少年保護が進まない日本の現状。しかし、過剰な規制にならないようにすることも必要
次に内山氏は、若年層のSNS利用の規制について質問。米国ではフロリダ州など多くの州で子どもがSNSアカウントを持つことを禁じたり、保護者の同意を義務付けたりする州法が制定されていること、オーストラリアでは、16歳未満の子どもたちによるSNSの利用を禁止する法案が可決されたことなどを踏まえ、「一方、今回の日本の法改正ではそこまでの規制はない。今後、日本でも若年層のSNS規制は行われていくのか」と尋ねました。
これに対し曽我部氏は、米豪の事例に加え英国でもオンライン安全法(Online Safety Act)が制定されるなど各国で青少年保護に向けた規制の展開が見られるとしつつ、一方の日本では「立法の動きという意味では全く進展がない。これは重要な課題だ」と語りました。そして、日本にも青少年インターネット環境整備法という法律はあるとしつつ、これは「二つの意味で時代遅れだ」と指摘。「一つは、対策がフィルタリングに偏っている点だ。例えば、X(旧ツイッター)はデフォルトでフィルタリング対象になっているが、ユーザー側がカスタマイズすればフィルタリングを外せてしまい、青少年が何ら配慮のないサービスにさらされるという事態になる。現状では、プラットフォーム事業者に対しては青少年に関する規律はない」「もう一つは、アダルトコンテンツを見せないことや、性被害のリスクがある不適切な出会いを防止するための、いわば昔ながらの青少年健全育成に有害と思われるものへの対策に集中している点だ。しかし現在は、メンタルヘルスの問題や闇バイトなどをはじめとしてリスクの種類が広範になっているが、そうしたものにも対応できる法律ではない。海外の法律はそうしたところにももう少し目配りがなされている」などと説明しました。
ただ曽我部氏は、「この検討が直接法改正に結びつくかどうかは分からない」と前置しつつ、自身が座長を務めるこども家庭庁の「インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ」では、論点整理をしている最中であるとも語り、こうした作業を通じて社会にリスク認識が広まることが、法改正につながることへの期待感を示しました。
成原氏はまず、米国の規制立法に関して、州によって違いが大きく「政治的あるいはイデオロギー的な背景をもとにつくられているという印象を受ける」と補足。次に、日本の規制のあり方に関しては、青少年インターネット環境整備法を改正し、「これまでは携帯キャリアにフィルタリングの提供を義務付けていたが、プラットフォーム事業者に対しても何らかの取り組みを求めることは考えられる」としましたが、その際には過剰規制にならないように留意する必要があるとも指摘。豪州のように青少年のSNS利用自体を規制してしまうことは「やり過ぎ」と評しつつ、「学校や家庭自体からストレスを受ける青少年も多く、SNSはそうした場から逃避できる『第三の場』としての積極的な意義もある」とし、上手くリスクに対処しながら「そうした子どもにとっての開かれた場を確保することも大事だ」と主張しました。
若江氏も、SNS利用自体を規制することは過剰な規制としてこれに反対しつつ、2009年に石川県で定められた「いしかわ子ども総合条例」に言及。小中学生に携帯電話を持たせないよう保護者に努力義務が課されたものの、スマートフォンが普及する中、単なる所持規制を改め、適正な活用に向けた取り組みを促すため、2022年に条例が改正された事例を紹介した上で、青少年にもSNSを利用させつつ、同時にリテラシーを向上させるような取り組みが望ましいとの認識を示しました。
もっとも若江氏は、プラットフォーム事業者に青少年保護のための対策を義務付けることは必要であるとも発言。SNSでアルゴリズムによって過度なダイエットに関するコンテンツが繰り返し表示されたことで、強迫観念にかられて拒食症になるケースを例示しつつ、こうした弊害への対応は必要だとしました。
日本には表現の自由に関する判例法理の積み重ねがある。米欧をモデルとするのではなく、独自のモデルを模索すべき
最後に内山氏は、表現の自由と、その自由の行使によって侵害される権利・自由とのバランスについて、「米国のように表現の自由を重視していくのか、それとも欧州のように個人のプライバシーなどを重視していくのか。日本はどのような方向に向かっていくべきなのか」と問いかけました。
若江氏は、「表現の自由とプライバシーの対立については、伝統的にこれまでの判例法理の積み重ねによって適法な批判と違法な名誉毀損の限界は、ある程度明らかにされている」ために日本がその線引きを米欧いずれかに合わせる必要はないと指摘。ただ、表現の自由を最大限に重視した米国では、プラットフォーム事業者が大きく成長した反面、「誹謗中傷やヘイトが蔓延する事態になってしまった」として、「日本がこうした表現の自由を過度に重視していく選択をしないということに関しては、すでに社会の共通認識となっているのではないか」との見方を示しました。
成原氏も、日本の立法や司法は「米国と欧州の双方を両睨みしながら、上手くその中庸を模索してきた」としつつ、「表現の自由と名誉やプライバシーなどの人格権をどう調整するかということについては、これまでの判例が上手くバランスを取っていたので、今すぐにどこかの国をモデルにする必要はない」と語りました。とりわけ欧州に関しては、偽情報対策の強化を進めているものの、これはロシアの脅威という地政学的な背景があると分析。ヘイトスピーチ規制が厳格であるのも、過去のユダヤ人迫害という歴史的背景があるとし、現在の規制がそうした歴史や政治の文脈上にある以上、「日本はそれらをそのままモデルにはできない。上手く取捨選択する必要がある」と注意を促しました。
曽我部氏は、米国では判例上も学説上も「極端に表現の自由が重視されている」と解説。隣国・カナダでは欧州のようにヘイトスピーチ規制は強化されていることを踏まえつつ、こうした表現の自由の強度の保障は、他国にはない米国特有のあり方であるとの見方を示しました。
同時に、日本の憲法学は米国憲法理論の影響を強く受けているために、表現の自由を極端に重視する学説が憲法の教科書でも通説・有力説として採用されているとしつつ、「個人的にはそこまで表現の自由を絶対視する考え方には根拠がないと思っている。だからこそ、判例も学説には全く従っていない」と主張。表現の自由が重要だということは大前提であり、広範な規制はすべきではないとしつつ、一定の幅の中でバランスを取りながら誹謗中傷やヘイトスピーチに対して、「国としてもう少し踏み込んだ対応ができるはず」と提言。同時に、「対応を打ち出すにあたって、学説の表現の自由論が『壁』となるような状況は健全ではない」などと語り、今後のさらなる議論の必要性を指摘しました。
