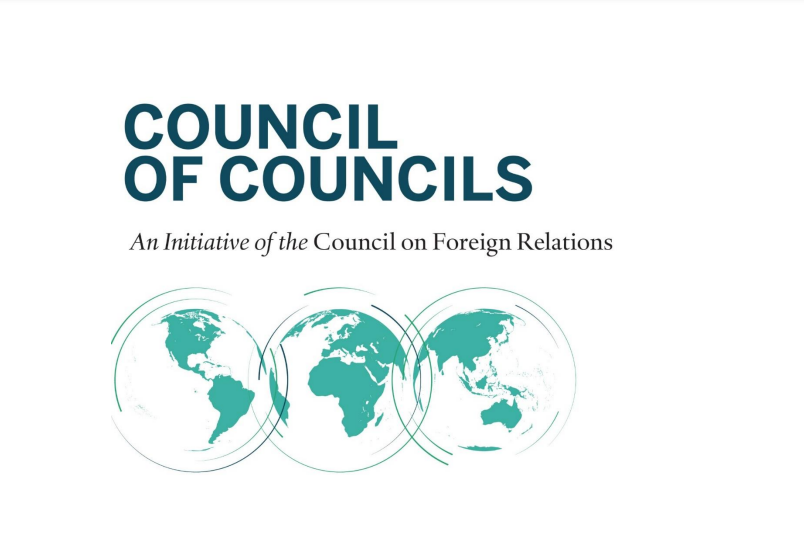ところが、世界は戦争を止めるために力を合わせられず、経済は分断やブロック化が進み、自国利益を優先する大国の力の行動が広がっています。その中で、気候変動や資源・食料、経済格差など、世界的なレベルでの課題への取り組みが進まず、世界は歴史的にも困難な局面に立たされています。
私たちは、日本こそがこうした課題に責任をもって取り組むべきだと考えています。そのため、私たちは世界を代表するシンクタンクとも連携して、この日本から世界の課題解決や多国間主義を守り抜き、世界の困難に力を合わせるための様々なメッセージを発信し続けています。
今、取り組んでいる議論
第二期トランプ大統領誕生から半年、世界はどう変わるか
 世界的な課題について、私たちが9月から10月にかけて取り組む議論は、トランプ大統領が進める米国を軸とする世界経済秩序は、本当に持続可能なものなのか、という点です。
世界的な課題について、私たちが9月から10月にかけて取り組む議論は、トランプ大統領が進める米国を軸とする世界経済秩序は、本当に持続可能なものなのか、という点です。
第二期トランプ政権発足から半年が経過し、日本では関税交渉ばかりが取り上げられていますが、トランプ大統領の狙いは基軸通貨ドル体制の下で生じた、米国にとって行き過ぎた不均衡を是正することであり、米国がドル体制をつくった原点に戻って、そこから米国の利益を再構築しようという試みだと我々は判断しています。 ただ、この行動によって世界経済の不確実性が非常に高まっただけではなく、米国も世界からの信用を失う事態を招いています。
トランプ大統領の試みは、本当に持続可能なものなのか疑問であるし、むしろ世界を大混乱に陥らせるのではないかということを、私たちは強く懸念しています。そのため、私たちは第一弾として「トランプ米政権は、関税措置で何を実現しようとしているのか」と題して議論を行いました。続いて、9月から10月にかけて3回の議論を行います。9月16日(火)には「トランプが主導する世界経済秩序は持続可能か」、9月17日(水)には「自由貿易体制はこのまま終わるのか」、そして10月17日(金)には「スティーブン・ミランレポートをどう読むか」を開催します。ぜひ、ご参加ください。
世界経済は「半ブロック」状態になる
第一弾として実施したトランプ関税についての議論では、伊藤萬里氏(青山学院大学経済学部教授)、福田直之氏(日本総合研究所主任研究員)、前田和馬氏(第一生命経済研究所主任エコノミスト)の3名にご参加いただきました。その中で、トランプ氏が打ち出した「相互関税」の目的については、貿易赤字解消はあくまで建前でしかなく、米国の世界経済に対する長期に渡る行き過ぎた不均衡を是正することであり、こうした米国の保護主義的な政策は今後も変わらないとの見方で一致。
中国との交渉では、レアアースの輸出規制で米国の方がダメージを受けている中で、90日間の延期が繰り返されるとの見方もありましたが、対抗関税の応酬になった場合、トランプ氏は三桁関税まで上げる リスクもま だ残っているという意見がありました。
今後の世界経済については、現在のサプライチェーンは複雑に絡み合っており、相互依存性が強いために戦前のような完全なブロック経済にはならないものの、「グループ分け」が起きて、「半ブロック」のような状態になるとの見方がありました。
日本の対応については、自由貿易を守るためにルールメイキングを主導することや経済連携協定をさらに拡大していく姿勢が非常に重要になると各氏は指摘しました。
参加者発言要旨
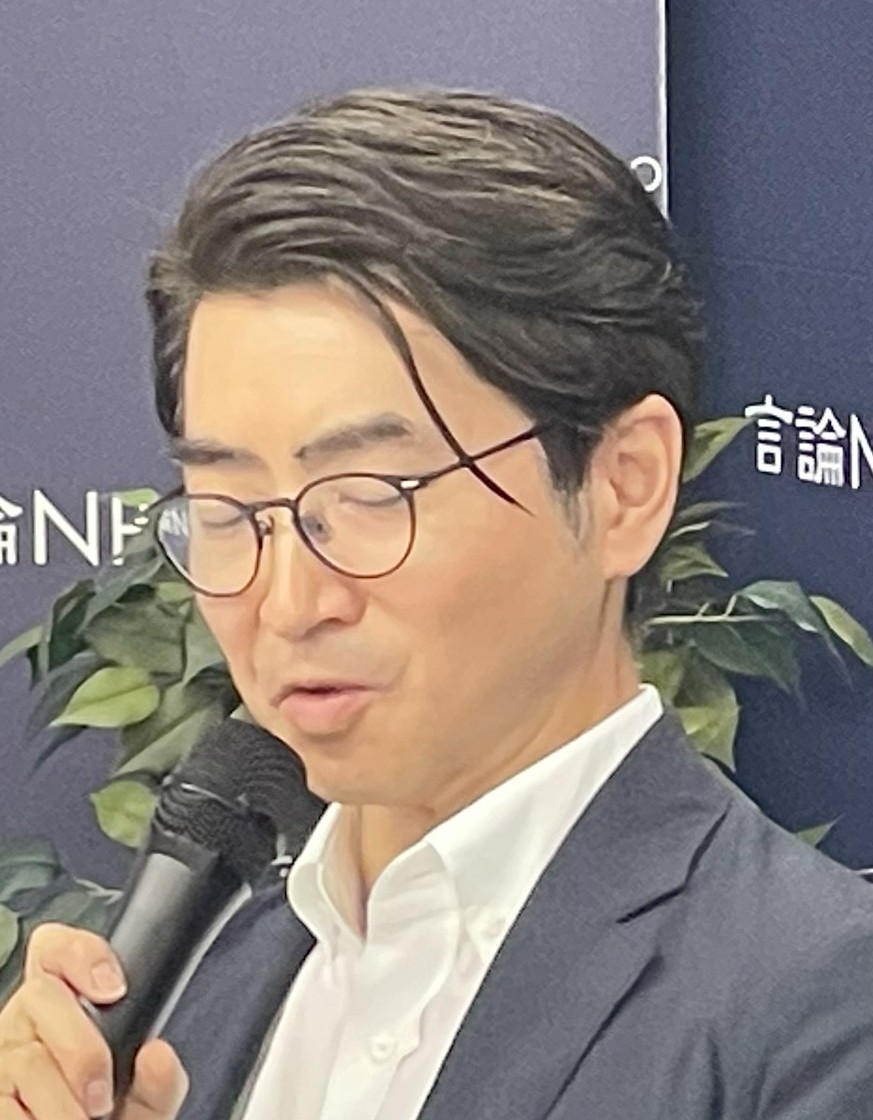 伊藤萬里(青山学院大学経済学部教授)
伊藤萬里(青山学院大学経済学部教授)
第一次トランプ政権時の対中関税が、「関税をかけると経済構成は悪化する」という教科書的にスタンダードな結果に落ち着いたにも関わらず、今回関税を強行したというのは、専門家から見ても意外だった。しかし、それでも関税をかけられた以上は、これがニューノーマルであるとして各国は対応していかなければならなくなった。
現在のサプライチェーンは相互に複雑に絡み合い、相互に調達しないと作れないものがたくさんある。そのため、サプライチェーンを完全に切断するという全く経済合理性がないことはどこもしないため、戦前のような完全なブロック経済にはならないだろう。もっとも、グループ分けのようなことは起きるかもしれない。
日本が取るべき対応としては、ルールメイキングや米国以外の国との間で経済連携協定のネットワークを広げていく姿勢が非常に重要になる。
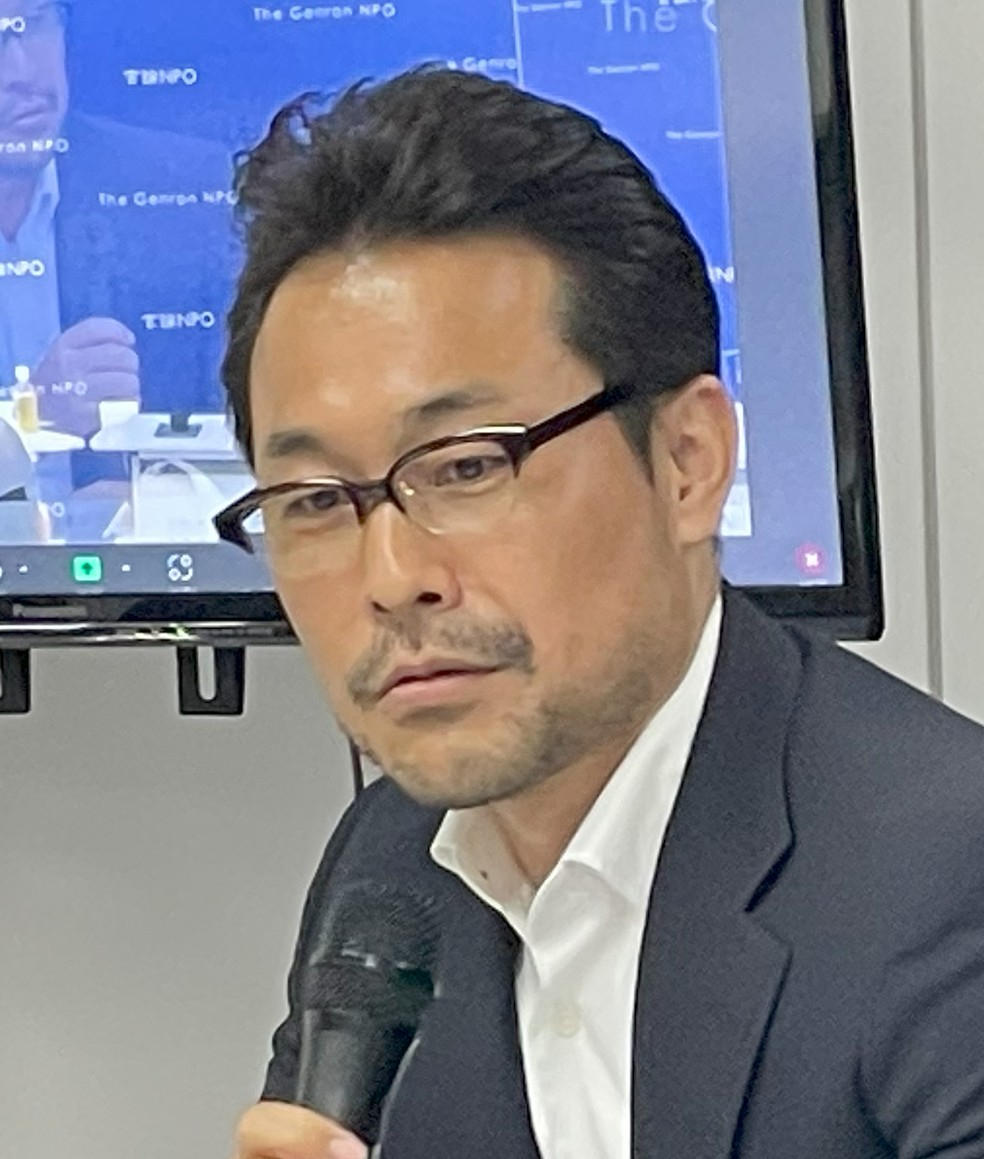 福田直之(日本総合研究所主任研究員)
福田直之(日本総合研究所主任研究員)
トランプ関税が目指しているのは、米国の再工業化と雇用の創出、それから減税の財源にして国内経済を活性化させることだろう。長期的には米国の対外不均衡是正というものを目指している政策でもあるが、それはおそらく上手くいかないだろう。
それでも、トランプ氏の考え方は約40年前から変わっておらず、大統領を支える側近も同じ考えのため、状況によっては当然関税を下げることもあるが、さらに上げることもあり得ることには要注意だ。こうした態度は、次の共和党候補でも民主党左派でも同様であり、米国がこの先バイデン・オバマの時代に戻るかというと、おそらく戻らない。
 前田和馬(第一生命経済研究所主任エコノミスト)
前田和馬(第一生命経済研究所主任エコノミスト)
トランプ関税の大きな目的としては、一つは製造業の雇用を回復するということ、もう一つは減税の財源にするという二つがある。このうち製造業の雇用回復については、この関税によって米国に全く雇用が戻らないということはないが、数百万人単位で戻るということはないだろう。
トランプ氏は中国経済にダメージを与えようと思っていたのだろうが、むしろ逆にレアアースの輸出規制で米国の方がダメージを受けている。もっとも、これは米中間の覇権争いでもあるため、米国が退くことは考えにくい。
世界経済の不確実性が高まる中で、他に日本が考えるべきこととしては、経済合理性の観点からなるべく余剰能力を削減してきたことの見直しだ。各企業は、地政学の混乱やサプライチェーンの混乱を織り込みながら、バッファーを持たせるような戦略のあり方を考えてもいいのではないか。